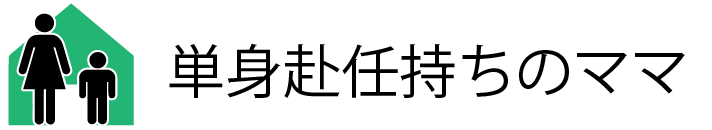大人になっても反抗期が終わらない人が多いと聞きます。
特に娘の立場である女性に多いようですが、今振り返ると私にも当てはまるような気がしてなりません。
私と同じように心当たりがある人いませんか?
そこで今回は、大人になっても終わらない反抗期の原因や対策について調べ、私の体験も交えてご紹介したいと思います。
今現在母親との関係に悩んでいる方、これから訪れる娘の反抗期に不安を感じている方の参考になればと思っています。
スポンサーリンク
関連のおすすめ記事
-

-
子育て中は1人の時間が欲しい。1人の時間の作り方と息抜き方法
子育て中は、ママが1人の時間を欲しいと思っても、実際は作ることが難しいもの。 特に子供が小さいうち...
スポンサーリンク
大人になっても反抗期が終わらないのはおかしい?反抗期が始まる時期とは
反抗期と聞いて一番に思い浮かべるのは思春期。
イメージとしては、小学校高学年頃から長くても高校生くらいを思い浮かべるのではないでしょうか。
しかし反抗期が始まる時期については、反抗期の程度はどうであれ、一般的には大人になるまでに3回訪れることがわかりました。
- 自我が芽生え始める2~3歳頃のイヤイヤ期
- 自分で考え行動する時期に差し掛かる小学校低学年頃
- 自立心が強くなる小学校高学年~高校生頃
一番多い反抗期、思春期に差し掛かる小学校高学年~高校生頃
この時期は子供から大人へと体も急激に成長する時期なので、ホルモンの影響もあるのでしょう。
特に女の子の場合は、これまでパパ大好きだったのが一変、急に嫌がって避けるようになるのもよくあることです。父親と洗濯物を一緒にされたくない、あなたも思春期の頃あったのではないでしょうか。
終わらない反抗期、そもそも反抗期はいつまで続くものなのか
あなたの周りにもいませんか?自分で反抗期はなかったと断言している人。
反抗期が始まる時期について述べましたが、これはあくまでも一般論であって、結局のところは反抗期の始まりも終わりも、人それぞれで個人差があるということです。
ただ反抗期は必ず誰しもが訪れることで、一見して反抗期がないように見えても、上手く言葉にできないだけだったり、表面上は今までと変わらなくても内心は悩んでいることもあり、暴力的な言動だけが反抗期とは限らないのが難しいところです。
反抗期は始まりも終わりも明確なラインが見えない
反抗期の終わりについても断言できない部分があるのです。
そして中には、大人になってもずっと反抗期が終わらないのか、親子関係につまづき悩んでしまう方もいるわけです。
反抗期が終わらないのではなく、単なるわがままではないのかという疑問
ホルモンの影響による体の変化、勉強、複雑になる友達関係、恋愛なども加わってストレスを抱え込みやすい時期でもあるのでイライラしやすくなること、しかし大人として自立するためには必要なことだというわけです。
今現在子をもつ親としても、反抗期とわがままの見極めも大切なのではと実感しているところです。
親が反抗期とわがままの見極めができない場合
子供のわがままを見過ごしてしまうと、反抗期が終わらないかのようなわがままな子供へと成長してしまいます。
反抗期の子供と親はどう向き合うべきか、これが「反抗期が終わらない」問題の解決の糸口になりそうです。
反抗期の子供に対して親がしてはいけないこと
子供の意思や気持ちを尊重せずに、干渉し過ぎること
子供には子供の世界がありますし、親に隠したいことだって1つや2つあると思います。
それなのに、勝手に部屋に入ったりスマホを盗み見したりするのです。子供が心配なのもわかりますが、これは一番やってはいけない行動の1つではないでしょうか。
子供が考えて出した答えに対して、親が否定的な言葉を投げかけること
子供の話に耳を傾けず、親の意見を押し通して頭ごなしに叱りつけるのもよくない行動です。
そうした行動を親からされると子供は親を信頼することができなくなり、何か問題が起きてもどうせ否定されるだけだと感じ、ますます反抗的な態度を取ったり逆に話さなくなります。
仲良くしているお友達のことを、何もわからずに否定されたとしたら。
子供を心配する親心からくる言動かもしれませんが、子供はますます反抗したくなるでしょう。
接し方で悩む娘の反抗期。子供への接し方のポイント
干渉し過ぎず見守る姿勢で
どれも親として子供に投げかけてしまう言葉ですが、思春期の子供に投げかけたところで「ウザい」と言われてしまうだけですし、「〇〇しなさい!」と声を荒げても子供と口論になってしまうだけです。
父親母親どちらかがフォローする役目を
父親よりも母親の方が子供と接する時間が多いと思います。
母親であるあなたと子供とで口論になり、頭ごなしに叱ってしまった時は、父親である旦那さんにはフォロー役に回ってもらうようにしましょう。
その逆でももちろんいいですが、このように父親と母親で違う役割を果たすことで、子供も落ち着きを取り戻しますし、それが理想の教育環境です。
夫婦協力体制で思春期の子供と向き合う、これも大切なことではないでしょうか。
子供が反抗期でギスギスしていても、夫婦仲良く居心地が良い家庭を保つ努力をする
子供が反抗期を迎え、親に対して暴言を吐いたり返事をしなくなったとしても、一番大切なのは子供が安心して過ごせる家庭環境を作っておくこと。
そのためには、夫婦仲も良好に保つ必要があります。
子供は夫婦仲に敏感です。夫婦喧嘩が絶えない家庭環境では、ますますストレスを抱えてしまうだけ。親に対して不信感を募らせることになります。
子供が反抗期でギスギスしていても、夫婦仲良く居心地が良い家庭を保つ努力をする、これも大切です。
「反抗期がこないのは危険」という話は本当なのか
「反抗期は成長の証。大人になるためには必要なこと」と同時に聞くのが「反抗期がこないのは危険」だという話。
これもよく耳にするフレーズです。
親としては、反抗期がないのは結構なことだと思ってしまいますが、反抗期がないと何が危険なのかも気になります。
そこには、幼少期からの親子関係が影響しています。
反抗期がこないというわけではなく、親に反抗ができなかったというのが正解でしょう。親が子供の意見を聞かず、過干渉だったり抑圧してきた背景が影響しているのです。
それが、反抗期がないのは危険だと言われている理由の1つです。
ただし、家庭環境に何ら問題なくても、反抗期がほとんどない子供がいるのは確かです。
だからといって対人関係に問題があるわけでもなく、親子関係が悪いわけでもないので、本人もわからずに反抗期を終えたのかもしれません。
反抗期は本当に個人差があるのだと思います。
終わらない反抗期。終わるきっかけは本当の意味での自立かもしれない
小中学生の頃は目に見える反抗期はなかったと思います。
高校生となり、義務教育とは違う自由を味わうことになりますが、そこから母親と口論が絶えなかったように感じます。
しばらく口を聞かずに過ごすこともありました。
進学で一度実家を離れましたが地元に就職したのを機にまた自宅に戻ったのですが、社会人になってからも学生の頃と変わらず口うるさく言われるようになったこともあり、また口論するようになりました。
大人になってからもずっと反抗的な態度をとっていた私ですが、親との同居に息苦しさを感じた私は、ずっと反対されていた一人暮らしをする決断をしました。
それまで一人暮らしに大反対だった母親でしたが、私の意思が固かったからか、母親自身も私との同居に疲れていたからか、意外とすんなりOKしてくれました。
この一人暮らしがきっかけで、今までの親子関係も改善されたように思います。
もう一つ良かったのは、母親と口論が絶えなかった一方で、父親は上手く間に入ってくれたことです。毎回母親と喧嘩するたびに、父親が上手くフォローしてくれていました。
反抗期はもちろん、親子でも適度な距離感が大切
反抗期の子供に対して親は見守る姿勢が大切なことでもわかるように、反抗期に限らず大人になった娘に対しても、あまり干渉せずに、見守ることも必要だと実感しています。
子供を心配するのは親として当然のこと
今は、あの頃の両親は娘の私を心配しての言動だったのだろう…とある程度は理解はできますが、思春期の頃はそんなこと当然ながら考えもしません。
ただ親となった今は、思春期の頃自分が嫌だったことだけはやめよう、そう心に誓っています。適度な距離感を保って子供たちを見守ろうと思っていますし、夫婦でそう話し合っています。