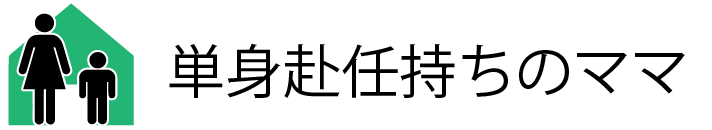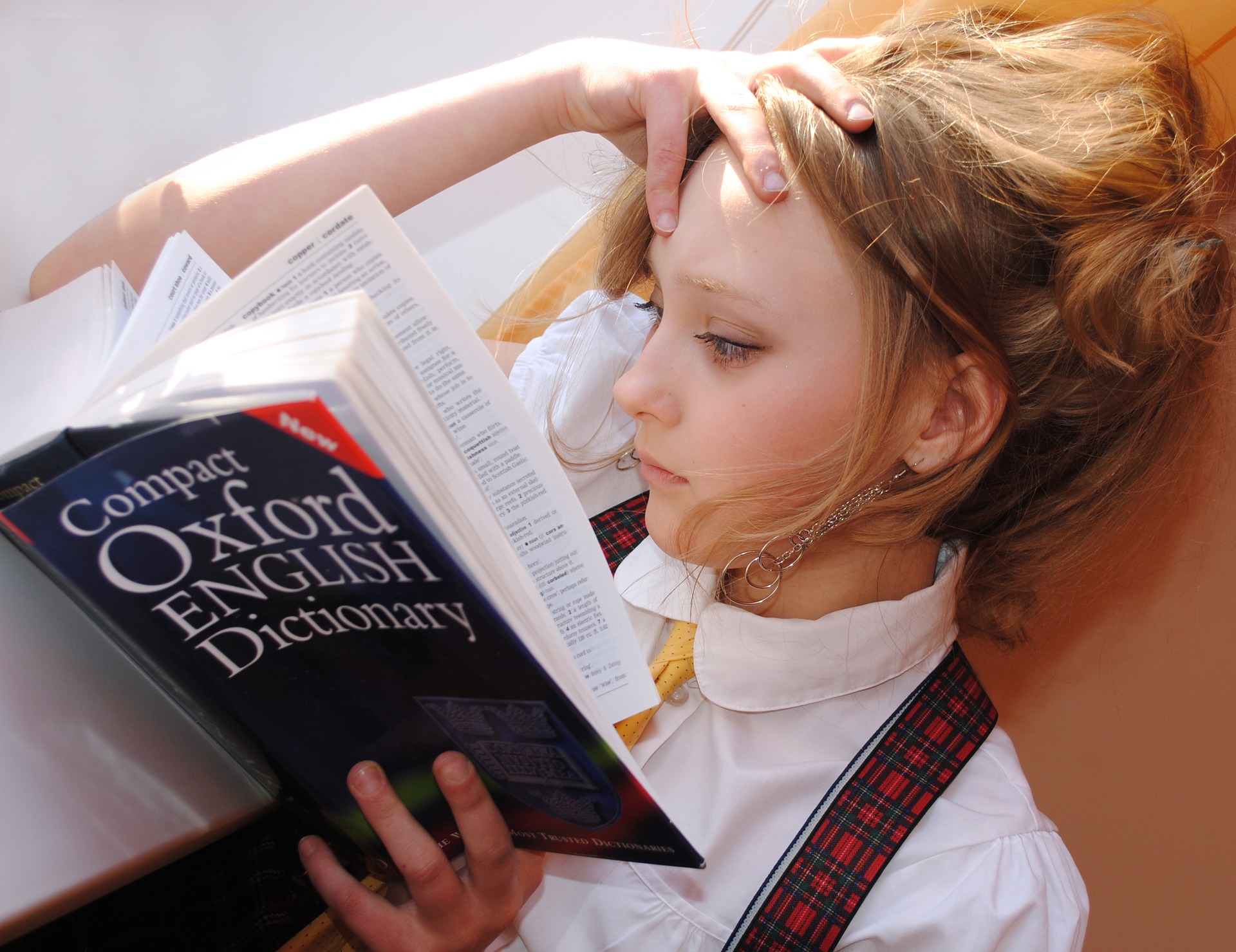子供のお小遣いはいつから始めるべきなのか、お手伝いをしてくれた時にお小遣いを渡す方法でもいいのかと悩んでいませんか?
子供にお小遣いを渡す方法の1つに、「報酬型お小遣い制度」があります。
玄関掃除○円、洗濯物を畳んで○円などのルールを決め、お手伝いをした分だけ小遣いを得られる仕組みです。
働いた分だけ報酬を得られる達成感がある一方で、お手伝い=お金という発想になりやすく、中途半端なお手伝いでもお小遣いを貰おうとしたり、貰う金額によってお手伝いを選ぶなどデメリットも含んでいます。
そこで今回は、お小遣いはいつから始めるべきなのか、お手伝いの報酬として渡すポイントや注意点について考えてみました。
スポンサーリンク
関連のおすすめ記事
-

-
転勤族が子供の学力に及ぼす影響や学校選び、母親の役割について
「転勤族です」と話した時に「転勤が多いと子供の学力に影響するから可哀想」と言われることがあります。 ...
-

-
子育て中は1人の時間が欲しい。1人の時間の作り方と息抜き方法
子育て中は、ママが1人の時間を欲しいと思っても、実際は作ることが難しいもの。 特に子供が小さいうち...
スポンサーリンク
お小遣いはいつから?お小遣いを渡すタイミング 我が家には小学生の子供が2人いますが、既に毎月お小遣いを渡しています。 子供にお小遣いを渡す年齢で多いのが小学生頃だと思いますが、それには理由があるからです。 数字がわかり、自分で管理でき[…]
お小遣いはいつから?お手伝いの報酬としてお小遣いを渡す方法は、意見が最も分かれるのはなぜなのか
お小遣いをスタートさせる時期は、各家庭の教育方針や子供の年齢も関係してきますので明確にいつからなどはありませんが、お小遣いをスタートさせる前には、子供とお小遣いについてしっかり話し合うことが大切です。
お小遣いを渡す4つの方法
- 固定型~毎月一定額のお小遣いを渡す方法
- 報酬型~〇〇掃除10円など、お手伝いをしてくれた報酬としてお小遣いを渡す方法
- 固定+報酬型~毎月のお小遣いと、特別なお手伝いをしてくれた時にその報酬としてお小遣いをプラスして渡す方
- 固定-減給型~毎月のお小遣いは渡すが、家庭のルール(決められたお手伝い)を守らなかった時にお小遣いを減らす方法
上記以外にも各家庭によってお小遣いの渡し方は色々ありますが、中でもお手伝いの報酬としてお小遣いを渡す方法は一番意見が分かれるところです。
という意見がある一方で、
という意見もあるからです。
いずれにしても報酬型のお小遣いは、受け取る子供の考え方によって左右されますので、報酬型のお小遣い制を導入する場合は十分注意が必要でしょう。
家のお手伝いによってお小遣いを与える報酬型のメリット
家のお手伝いをしてくれた報酬として、その都度お小遣いを渡しているご家庭もたくさんいると思います。
報酬型お小遣いのメリット
- 労働の対価としてお小遣いを渡すことで、お金のありがたみがわかる
- 進んでお手伝いをするようになる
- 責任感が芽生える
- 世の中の仕組みを理解しやすい
- 働いて稼ぐ大変さがわかる
などがあげられます。
お手伝いの報酬としてお小遣いを貰うことで、今まで普通に買っていた100円のお菓子も、
と考え方が変わります。
働いてお金を稼ぐことの大変さを知ることで、お手伝いで得たお金を大切に使おうという気持ちが芽生えますし、働いてお金を稼ぐのはこんなに大変なことなんだと身にしみて感じることができるのは、報酬型お小遣い制度の大きなメリットではないでしょうか。
デメリットは、お手伝いをしたんだからお金が欲しいと見返りを覚えてしまうこと
一方デメリットについて考えた場合、
- お金目当てでお手伝いをするようになる
- 報酬が高いお手伝いしかしなくなる
- お手伝いをお願いするたび「それいくら?」と聞くようになる
- お金が発生しないお手伝いはしなくなる
- お手伝いが面倒になり、お金はいらないからお手伝いをやめると言い出す
などがあげられます。
確かにこれらを見ると、自分が子供の立場だったら確かにそうだなと思えるものばかりでです。
家のお手伝いは、「相手を思いやることで生まれる行為」
「ママが忙しそうだからお風呂掃除をしよう」
「玄関が汚れていたらお客さんが来た時に困るから片付けよう」
「自分の洗濯物くらい自分で畳むようにすれば、ママの負担も軽くなるかも」
という思いやりから、よし、お手伝いをしよう!と考え行動するのではないでしょうか。
それがお手伝いの報酬としてお小遣いを渡してしまうと、思いやりによるお手伝いがなくなってしまい、お手伝いをしたからお金が欲しいといった見返りを覚えてしまう危険性もあると思います。
報酬型お小遣い制度を導入する際はお手伝い表を活用しよう
では、報酬型お小遣い制度を導入する場合はどうすればいいのでしょうか。
お手伝い表を作る
カレンダーのようなお手伝い表を作り、お手伝いをしてくれた時にその表に記入していく方法です。
お風呂掃除〇〇円などルールも記入し、その日お手伝いをした内容と金額も記入してくのですが、お手伝いのたびに「はい〇〇円」と渡すのではなく、お小遣いを渡す日を決めて集計を行なってまとめてお小遣いを渡すといいでしょう。
表にすることで自分の頑張りや金額が見えやすく、いつ何のお手伝いをしたか親ももわかりやすいと思います。
子供の頑張りを褒め認めてあげる
お手伝いの報酬としてお金を受け取ることは、会社で働いてお給料を貰うことと同じことです。
頑張った分だけお金が貰える達成感はもちろん、その頑張りに対して褒めて貰えるとモチベーションは高まります。
お手伝いによる報酬型お小遣いは小学校1年生からでも始められるが、高学年からは固定+報酬型導入がおすすめ
お小遣いを始める年齢についても意見が分かれるところですが、このお手伝いによる報酬型お小遣い制度については、小学校1年生からでも始めやすい制度だと思います。
お手伝いをしないとお小遣いを得られないため、お金の価値を知るためのスタートにもなるのではないでしょうか。
子供も成長と共に知恵が尽きますし、報酬型が逆に悪い方向へ傾いてしまう可能性があるからです。
そこでおすすめしたいのが、固定+報酬型制度の導入
高学年にもなると自分で買いたい物が増えますし、月に決まったお小遣いを渡すことで使い道の見通しが立てやすくなります。
お小遣いをいつから渡すべきか、どんな方法でお小遣いを渡すべきか親は悩みますが、意見が分かれる報酬型お小遣い制度を導入する場合は、メリットやデメリットを理解した上で、家族で話し合ってルールを考えることが大切です。